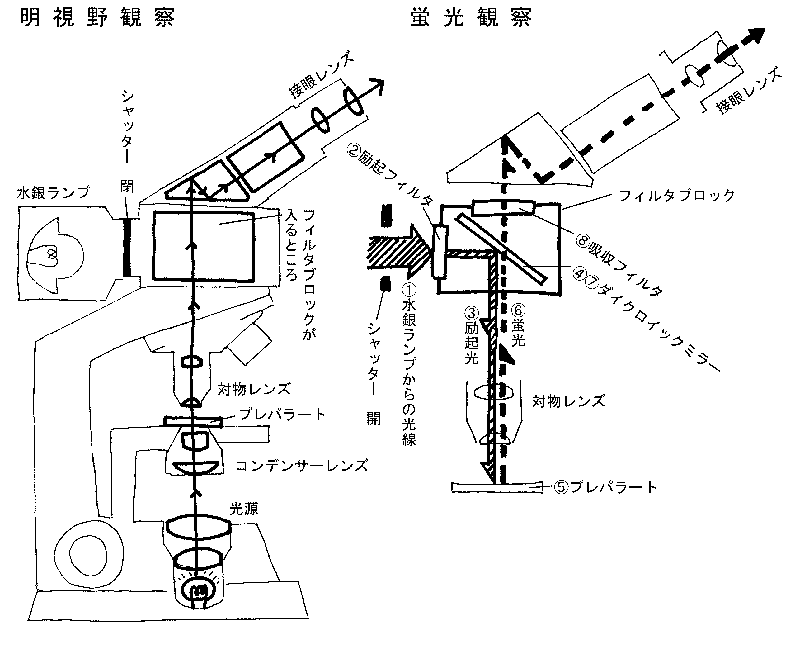
蛍光色素で染めた試料に励起光を当て、発する蛍光を観察する顕微鏡です。
励起光に対して蛍光は大変弱いので、視野に励起光を入れないようにする必要があります。
そのためにフィルターブロックと呼ばれる特殊なフィルターのセットを使います。
図の左は蛍光顕微鏡で明視野観察(普通の顕微鏡)を行っているときの図です。
フィルターブロックを入れてありません。また、水銀ランプは消灯しシャッターも閉めた状態です。
光源からの光はプレパラートを透過し対物レンズ、接眼レンズを通り眼に像を作ります。
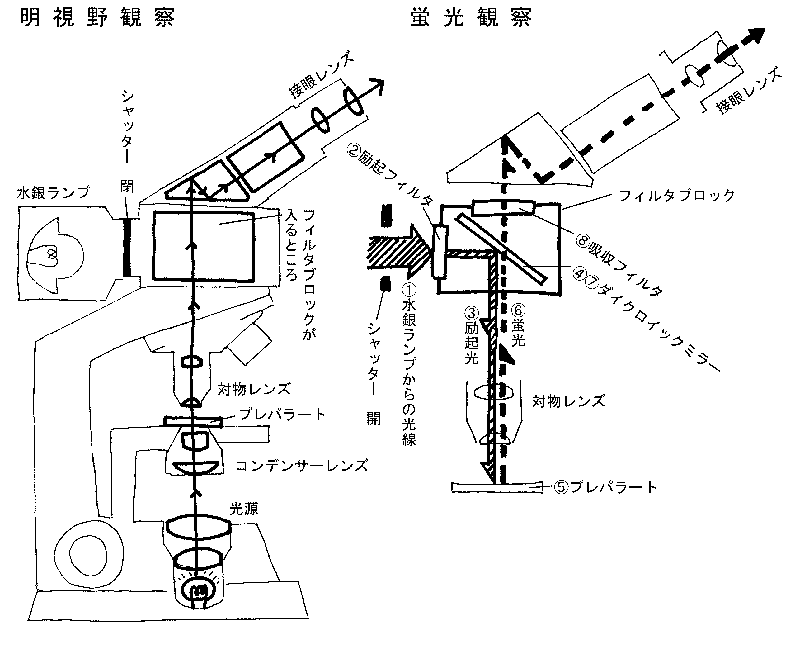
図の右は蛍光観察を行っている図です。
レバーやターレット(ダイヤル)を操作してフィルターブロックをセットします。
水銀ランプを点灯し、シャッターを開けます。
①水銀ランプの光には可視光と紫外線が含まれています。
②励起フィルターは励起光だけを透過します(B励起なら495nmの青色光)。
③励起光は④ダイクロイックミラーに当たります。ダイクロイックミラーは励起光を反射させる特殊な加工がしてあります。
③ダイクロイックミラーで反射した励起光は対物レンズを通り⑤プレパラートを照射します。
⑤プレパラートの蛍光色素は励起光によって⑥蛍光を発します(B励起なら519nmの緑色光)。
⑥蛍光は対物レンズを通り⑦ダイクロイックミラーに当たります。⑦ダイクロイックミラーは励起光を反射し蛍光を透過します。蛍光はダイクロイックミラーを透過し⑧吸収フィルターに達します。
⑧吸収フィルターは蛍光だけを通します。余分な光はここで吸収され、蛍光は接眼レンズを通り眼に像を作ります。
励起光の一部はプレパラートで反射して対物レンズに入りますがダイクロイックミラーと吸収フィルターで遮られ視野には入りません。
この様に蛍光顕微鏡ではフィルターブロック、特にダイクロイックミラーが重要な役割を果たしています。